
秋分の頃 町石道から里山を訪ねて
秋分(九月二十三日頃)
秋の彼岸の中日で、昼と夜の時間がほぼ同じになる頃で、暑い日は減り、代わりに冷気を感ずる日が増えます。秋の七草が咲きそろう時期となります。

秋分の頃、里山はヒガンバナ(彼岸花)の鮮やかな赤に彩られます。
特に朝露に濡れて、瑞々しくも華やかに咲く深紅の花は、その形の特異さとも相まって何か浄土の世界を写したかのような雰囲気を漂わせています。
黄色く色づいた稲の波を背景に、たんぼの畦道に沿って咲く彼岸花に遠い昔の思い出を重ね合わせる人も多いのではないでしょうか。
花輪を作ったり、竹の棒でなぎ払ったり、球根を掘り起こしたり、人それぞれに思い出は違えども、秋の彼岸の頃になると決まって咲き乱れ、田舎道を赤く染めたものでした。
その雰囲気を里山に求めてみたくなり、三日間の連休を町石道につながる五つの里に彼岸花を訪ねて歩くことにあてました。五つの里とは、九度山の里、山崎の里、天野の里、神田の里、そして細川の里のことです。
彼岸花に引かれて訪ねた里山には、他にも私を迎えてくれる草花が待ち受けてくれていました。
いつものように慈尊院をスタートし、柿畑にある百七十八町石にさしかかって上を見ると、そこに彼岸花がかたまって咲いているのを見付けました。その一群を町石の前に配した構図で写真を撮りたくて斜面をよじ登り、ファインダーを覗くと思ったような構図になっており、まずは目的のものをゲット。
実際に何枚かを写真に撮って見ると、鮮やかに咲く赤い花の集団に強烈な個性を感じました。周りの景色と調和させるには、少し控えめが良さそうです。
百五十六町石の分岐点を右にとると山崎の里に出ます。しばらく舗装された下りを進んだとき、再び赤い固まりが目に飛び込んできました。柿畑の一山が彼岸花で覆われていたのです。畦道に細長く咲く彼岸花は何度も見たことがありますが、こんな状態で咲いているのは始めてみました。
柿の木畑に赤い絨毯を敷き詰めたような光景が、なかなか壮観でした。

それに加え、里山では今、シシウド(獅子独活)が花を付けていました。中心から放射状に空に向かって咲く白い花が印象的です。青い空に白い花を浮かび上がらせて撮ると、まるで白い花火がはじけたようです。
形がウドに似て、猪が食べるに相応しいほどたくましいということから付けられた名だとか。茎が出るまでに四、五年かかり、一度花が咲いて実を結ぶと枯れてしまうそうです。
土曜の午後など時間に余裕のない時は、九度山から町石道を通り、山崎に抜け、三谷橋を渡って紀の川道を辿る四時間あまりの歩きを楽しむことにしています。町石の道、里山の道、川辺の道を一度に楽しめるお気に入りのコースです。
他にも、百四十五町石から右にそれて、紀の川の流れを下に見ながら、かつらぎの尾根道を歩くコースもおすすめです。 第一日目は、彼岸花とシシウドをカメラに収めることができ、この三連休の手応えを感じました。

連休第二日目は、町石道を通り、六本杉から天野の里におり、しばらく散策したのち、八町坂から二ツ鳥居に出て、再び町石道をとり、道沿いにある神田の里を訪ねたあと、矢立から細川の里を辿るというコースです。
昨日、右にそれた百五十六町石を直進し、石ころの多い上り坂を進みます。雨引山への分岐点を通過して杉林にさしかかったとき、道端にホトトギスの花を見付けました。日当たりが悪いせいもあって大きく成長していませんが、一輪挿しのようにボツボツ咲いているのが可愛く感じられました。この花は日当たりのよいところより、やや湿ったところを好むようです。初めてこの花を見付けたとき、噴水のように二段になって花が咲いているのを珍しく思いました。それに、ホトトギスという名に意外性を感じたものです。
赤みがかった濃い紫色の斑点が、ホトトギスの胸の模様に似ているところから名付けられたと言うことです。町石道に咲いているのは、形からして、正確にはヤマジノホトトギス(山路のほととぎす)のようです。
天野の里に下りる道端にもたくさん咲いており、枝先に止まった赤トンボが秋を演出してくれていました。

天野の里に降りてみると、丁度稲刈りの時期でした。コンバインが田圃の外枠から内に向けて稲を刈り取っていました。天野の里の田圃は国の事業で区画整理されており、四角く区割りされているからこのような苅り方ができるのでしょう。
思ったほど彼岸花が少ないのも区画事業のせいかもしれません。昔は、毒性のある彼岸花を利用して虫よけのために畦道に生やしたものですが、その必要が無くなったのでしょう。
彼岸花は葉が出る前に茎が長く伸びて、その上に大きな独特の真っ赤な花を付けることは周知の通りですが、その特長を生かして、地面すれすれから茎の間に見える天野の山や空の景色を撮りたくて里に下りてきたのです。槇の林に咲く彼岸花で何とか目的を果たしましたが満足のいくものではなく、来年に課題を残しました。

丹生都比売神社の朱色の太鼓橋を通り、天野神社に手を合わせた後、八町坂を辿って二ツ鳥居に至り、再び町石道を神田の里目指して歩きました。
神田の里ではすでに稲刈りも終え、稲木に稲の穂を束ねて干した状態でした。その景色が秋の風情を醸し出していましたが、彼岸花は一見して見あたらず、里に下りていくのを止め、ひたすら矢立を目指しました。そこから左に折れ、町石道から離れました。勿論、彼岸花が目的だからです。そして、ねらっていた風景がそこにありました。
山間の田圃の畦道に咲く彼岸花です。杉林を背景に、黄色く色づいた稲穂と二つの田圃を仕切る畦道沿いに赤い彼岸花が筋になって咲いており、里山ならではの構図を形取っていました。それに加え、山崎の里でも目にしたシシウドもたくさん生えており、薄暗がりの里に白くぼやけて浮き上がっていました。
満足した想いで紀伊細川駅に辿り着いて見ると、そこには更に私を喜ばせる最後のプレゼントが待ち受けていたのです。
駅の左手下の階段の両側に彼岸花が連なって咲いており、下から見上げた構図がいかにも山間の駅らしく鄙びた感じでした。

連休も最後の三日目となりました。
矢立から大門まで最後の三分の一を上ることになります。五つの里山を訪ねるという目的は昨日までに果たせたので、目にするものを気楽にふれながら登ることにしました。
昨日までに見かけた以外で秋を感じさせるものは何かないかな、という期待に応えてくれたのがミズヒキソウ(水引草)でした。
高野山駅から極楽橋駅をつなぐケーブルカーのアナウンスでも秋のミズヒキソウが紹介されています。
上から見ると赤、下から見ると白に見える花穂を、紅白の水引に見立ててこの名が付いたそうです。茶花によく利用される楚々とした花です。
細長い花軸にまばらに小さな花が付いており、バックの景色に吸収されるようで、カメラにとらえるのが難しく感じられました。何とか木の根っことか、茂みの影を利用して、細長い軸が浮き上がるように工夫しました。

ミズヒキソウと同じように、細長い姿のアキチョウジ(秋丁字)が、その名の通り、秋の町石道の各所に丁字形の花を咲かせていました。触れるとぽろぽろとこぼれそうな感じで薄紫の花を付けており、花ひらを強調して写し込むにはかなり苦労しました。
高野山展望台で一休みした後、下っていくと高野山道路の向かいに三十七町石が見えます。 実は高野山の有料道路が出来た頃、この町石にとっては受難の時でした。町石道が寸断され、工事に巻き込まれて折れたり、埋もれたりした町石がかなりありました。

道路をそれて、小高い見晴らしのいいところに展望台が作られています。四十町石がその登り口にあり、降り口に三十七町石があって、三十九町石、三十八町石の二基は展望台下の高野山道路沿いにあるのです。 時折、展望台に向かわず、高野山道路を歩いてこの二つの町石を写真に収めるのですが単車や車がひっきりなしに通るので落ち着きません。他にも三十三町石のように、高速道路沿いに立っていたものを今の位置に移設したものもあります。
三十七町石を道路の向かいに見ながら町石道は右に折れ、大門に向かいます。直ぐのカーブの地点にはススキが群れて咲いており、その上がコンクリート壁になっていて往来する車の音が聞こえます。

ススキを写真に収めてから、少し先に行ってピタッと足が止まりました。今まで探し求めていた三十六町石が突然姿を現したのです。
ここから少し向こうに四里石があり、案内図によると、この近くにあるはずの三十六町石をどうしても見付けることが出来ませんでした。この辺りを何度もうろついたのですが探し当てることができずにいました。それが今日、忽然と姿を現したのですから驚きです。
生い茂るササにすっぽり埋もれてしまって、町石道からは姿を隠していたのでした。それが、世界遺産に登録するための誘致運動の一環として町石道が整備され、全ての町石が見えやすくするために周りのササを刈り取ったので、日の目を見たというわけです。
これで、百八十基の町石と四基の里石を全て写真に収めることが出来ました。これだけでも今日歩いた価値があろうというものです。心弾ませてながら、角度を変えて何枚も写しました。

大門下に群生するミカエリソウにも花が付き始めました。花穂の下からうすいピンクの花がほころび出したのです。だんだん咲上がって、来週にはピークを迎えることでしょう。
秋分の日を含め、三日間の連休に秋を求め、町石道を軸にして五つの里山を訪ねた試みは成功でした。彼岸花に焦点を合わせていたのですが、歩いてみるといろいろな花が私を迎えてくれていました。
シシウドやホトトギス、ミズヒキソウなどは本文中でも紹介しましたが、他にもヌルボ、イタドリ、ハギ、ススキ、オミナエシ、オトコエシなど、それぞれの姿で秋を彩っていました。
緑の夏を越え、秋の草花に季節を感じながら、三日間の連休を町石道で楽しみました。

笹田義美先生のプロフィール
販売のご案内
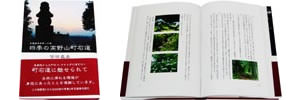
世界遺産登録への道「四季の高野山町石道」
- 著者
- 笹田 義美
- 定価
- 2,800円(税込)
- お問い合わせ
- TEL. 073-435-5651
![ウォーカーステーションTV [WSTV]](../../images/common/logo.png)

